貝原益軒は江戸時代の庶民のための教育家で、子どもの年齢に応じた教え方として「随年教法」(教育課程論)を示した。
小学校何年生レベル、とかもここから来てるのかな?
気にしたことなかったけど、世界中で年齢に合わせた学習内容とか違うしその子によっても違うんだよね。
同じ人間が1人もいない中で同じことを学ばせていくカリキュラムを作ったことも凄いと思うけど、それによって失われていくその人の味というか、魅力がもったいないなと思う。
何にでもレベルがつけられる中で、ついていけない人や逆に飛び級していくような人がいて、カリキュラムに沿ったことができると卒業できて、それが印象につながっていて。
施設に入った時、転校先の学校に通えなかった。担当の職員にもいい加減にしなさい、ふざけるなと言われた。
休みたいと伝えた時、甘ったれてんじゃねーよって言われた。
別の棟の職員さんが来て、コンコンと説教された日もあった。学校はね、行かないといけないよ、あなたの将来のためを思って伝えるけど、本当に行っといた方が良いよ。1時間くらい、とても心を込めて伝えてくれてるのはわかるけど、何も伝わって来ない、この人は何もわかってないなと思う時間だった。
大人が伝えることは既に心の中で、学校にいる中で、学校のトイレの中で、何百回も自分に言い聞かせてきた事だったから、もう聞き飽きてて。
心が腐らない教育課程論があっても良いんじゃないかと思った。
数字では測れないものを見つめられる先生がいる学校って素敵だなと思う。学校では無くても、身近にいる大人に1人でもそういう目を持っている人に出会える事で、生きる勇気とかその子が大人になっていく時に自分の在り方を選ぶ選択肢の指針になっていくと思った。

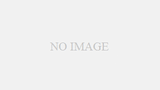
コメント